

救命センターブログ
新潟ドクターヘリ2号機

救命センターブログ
トラクター、コンバインの悲惨な事故
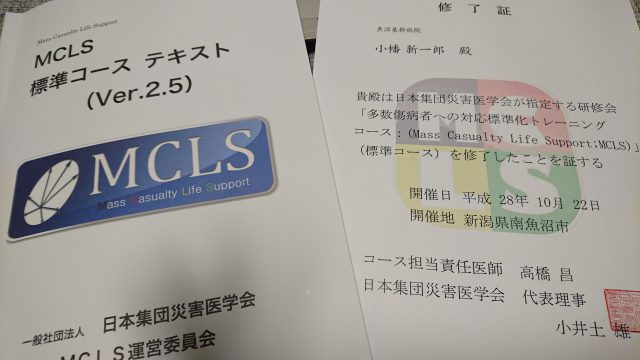
救命センターブログ
MCLSを受講してきました

救命センターブログ
柿の木外傷

救命センターブログ
停電検査

救命センターブログ
火災・避難訓練

救命センターブログ
東北ブロックDMAT実働参集訓練

救命センターブログ
あわてず安全農作業

救命センターブログ
夏もおわり

救命センターブログ
初めてのメディカルラリー

救命センターブログ
地域のイベント。住民とふれあえた鮎祭り。

救命センターブログ
JPTEC

救命センターブログ
英語トレーニングプログラム~救急編~
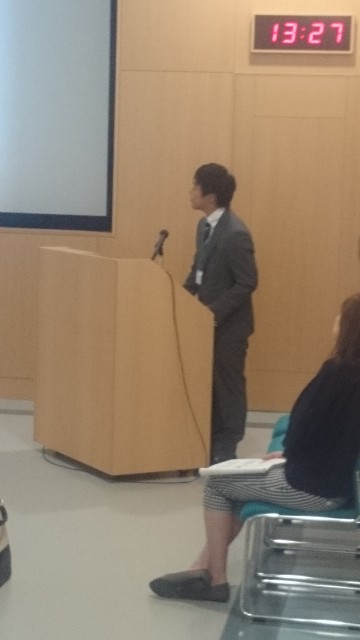
救命センターブログ
勉強会に参加して ~振り返りと、反省と。~

救命センターブログ
災害研修のこと

救命センターブログ
第1回うおぬまメディカルラリー開催で、さらなるチーム力アップ

救命センターブログ
救命センター新人看護師奮闘記 ~激動の1年を振り返る~

救命センターブログ
感染性胃腸炎が流行してきています!!

救命センターブログ
私が魚沼基幹病院救命センターにいる理由

救命センターブログ
こどもの発熱

















 連絡先を知りたい
連絡先を知りたい  診療スケジュールを見たい
診療スケジュールを見たい  行き方を知りたい
行き方を知りたい  救急外来を受診したい
救急外来を受診したい  これからご入院される方へ
これからご入院される方へ  里帰り出産について知りたい
里帰り出産について知りたい  患者さんを紹介したい
患者さんを紹介したい